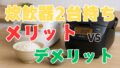「玄米の炊き込みご飯って健康に良さそうだから作ってみたけど、なんかまずい…」そんな経験ありませんか?
食感が硬かったり、芯が残っていたり、味が薄かったりと、「白米の炊き込みご飯より難しい」と感じる人は少なくないはず。
でも、それって実はちょっとした工夫で解決できるんです!
この記事では、「玄米の炊き込みご飯がまずい」と感じてしまう原因と、それを劇的に改善する方法をわかりやすく紹介します。
健康的で美味しい玄米ご飯を、無理なく楽しみたいあなたへ。コツさえ押さえれば、もう失敗知らず!
- 「まずい」と感じる主な原因とその正体
- 玄米をふっくら美味しく仕上げるコツ
- おすすめの具材&調味料で味に深みをプラス
- 初心者でもできる失敗回避テクニック
【玄米の炊き込みご飯】まずい原因は?よくある失敗ポイントとは

硬くてまずい!「芯が残る」原因とその正体

玄米の炊き込みご飯が「硬い」「芯が残る」と感じる最大の原因は、ずばり浸水不足です。
白米と違って玄米は表面にぬか層が残っているため、水を吸収するのに時間がかかります。
これを無視してすぐ炊いてしまうと、中まで水が届かず、パサパサ&芯が残る仕上がりに…。
理想の浸水時間については下の記事で詳しく解説していますので参考にしてくださいね。
それと、浸水中は途中で1回水を替えると、においの元となる雑菌の繁殖も抑えられ、よりクリアな味わいに仕上がりますよ。
私も最初は「玄米って硬いし、美味しくないなぁ」と思ってましたが、ちゃんと浸水するだけで驚くほど柔らかくなるんです!
芯が残ってると感じたら、まずは浸水時間を見直してみてくださいね。
浸水を侮るなかれ…ですね(笑)。
水加減だけじゃない!炊飯モードの落とし穴

意外と見落としがちなのが、炊飯器のモード設定。
最近の炊飯器には「玄米モード」がついているものも多いですが、それを使わずに白米モードで炊くと、火加減や炊飯時間が合わずに失敗しがちです。
玄米モードは、吸水時間や蒸らしを自動で調整してくれる優れもの。
炊飯器にこのモードがあるなら、迷わず使いましょう。
ない場合は、白米モードでも対応可能ですが、浸水と水加減の調整は必須になります。
個人的には、玄米モードを使うと「何これ!? 本当に玄米!?」っていうくらいふっくらして驚きました(笑)。
一度試してみると、その差は歴然ですよ!
具材が原因?「まずさ」を引き起こすNG食材とは

「玄米炊き込みご飯って、具材を入れると余計にまずくなる気がする…」
そんな人は、具材の水分量や切り方を見直してみましょう。
たとえば、水分を多く含む具材を大量に入れると、ご飯がべちゃっとなってしまいます。
特に、しいたけやしめじなどのきのこ類は旨味を出してくれる反面、水分が多めなので、入れすぎると炊き上がりがベチャベチャになりがち。
また、具材の種類によっては炊飯中に水分を吸いすぎてしまい、結果的にご飯が硬くなることもあります。
逆に水分が少ないものばかりだと、パサつきや芯残りの原因に。
じゃがいもや豆類などを使うときは、水加減や一緒に入れる具材で調整すると良いですね。
大事なのはバランス。
きのこやごぼう、にんじんなどの野菜は相性抜群ですが、大きく切りすぎると加熱ムラの元になるため、1cm角や薄切りを意識すると全体が均一に仕上がります。
また、市販の「炊き込みご飯の素」などを使うときも要注意。
すでに調味料や水分が含まれていることが多いので、通常よりも水を減らさないと、炊き上がりがべちゃつく原因になります。
私の場合、きのこをたっぷり入れたら旨味がアップして美味しくなったんですが、調子に乗って入れすぎたらベチャベチャに…。
しかも、大きめに切ったごぼうが一部だけ固かったりして「あれ?」って感じに。
加減って本当に大事だなって学びました(笑)。
具材選びも料理のセンスの一部ですね〜。
味がぼんやり…「めんつゆ」で旨味を引き出す方法

味が薄い・ぼんやりしていて「なんか物足りない」と感じるときにおすすめなのが、めんつゆの活用です。
めんつゆには出汁と調味料がバランスよく含まれているので、簡単に旨味を加えることができます。
特に、昆布や鰹の出汁が含まれているタイプは、玄米の香ばしさとよく合い、味に奥行きを持たせてくれるんです。
目安としては、玄米1合に対して大さじ1〜2程度。
これだけで味に深みが出て、まるで料亭のような仕上がりに。
あとはお好みで醤油や酒、みりんを加えて調整してもOK。濃いめが好きな方は、しょうがやにんにくのすりおろしをほんの少し加えるのもおすすめです。
また、味にアクセントをつけたいときは、塩昆布や干ししいたけの戻し汁をプラスするのもアリ。
これだけで、玄米のクセが和らぎ、うま味がグッと増します。
市販のめんつゆを使えば時短にもなりますし、調味料に迷ったときの強い味方です。
私も最初は「炊き込みご飯にめんつゆ?」って半信半疑でしたが、試してみたら驚くほど美味しくなりました!
「こんなに簡単でいいの?」って思えるくらい。
調味料にこだわるだけで全然違いますよ〜。
一度試すと、きっと手放せなくなります!
実はやりすぎ?ヘルシー志向が失敗を招くワケ

最近は「ロウカット玄米」が人気ですが、これも使い方を間違えると失敗の原因に。
ロウカット玄米は、玄米特有のぬか層を一部カットしているため、浸水時間が短くて済むというメリットがあります。
しかし、通常の玄米と同じ調理法で炊いてしまうと、水加減や炊飯時間が合わずに仕上がりがイマイチになってしまうことも。
さらに、ロウカット玄米はその性質上、ぬかの香りや風味が控えめな分、調味料の味が強く出やすくなります。
そのため、炊き込みご飯にした際に「味が濃すぎた」と感じるケースも。
シンプルに塩やだしで味付けする方が、素材の味が引き立ってバランス良く仕上がります。
「健康のために」と玄米に切り替える人は多いですが、白米と同じ感覚で作ると「まずい!」ってなりがち。
ロウカット玄米はあくまで“玄米より扱いやすい白米寄りの存在”なので、炊飯モードや水加減も専用の調整が必要です。
また、炊飯器によってはロウカット対応モードがある機種もあるので、取扱説明書を確認してみるといいですよ。
私も最初は「ロウカットなら簡単でしょ」と油断して失敗しました…。
水を入れすぎてベチャベチャになったり、炊き込みご飯にしたら調味料の味が強すぎてしょっぱくなったりして、がっかりした経験があります。
でも、ちゃんとパッケージの指示どおりに水加減と浸水時間を守ったら、見違えるほど美味しくなったんです!
玄米にもいろんな種類があるので、見た目や名前に惑わされず、それぞれの特性を理解して使うのが大事ですね。
意外と奥が深いんですよ、玄米って。
【玄米の炊き込みご飯】まずいを卒業する!美味しく作る4つのコツ

浸水は12時間が理想!玄米の下準備の鉄則

失敗の原因でも述べましたが、玄米を美味しく炊き込みたいなら、まずは「浸水」にしっかり時間をかけましょう。
目安は最低でも6時間、できれば12時間以上。
浸水時間をしっかり取ることで、玄米の芯まで水が行き渡り、ふっくら柔らかく仕上がります。
特に寒い季節は水温も低くなりがちなので、室温での浸水では吸水が進みにくくなります。
そんな時は、ぬるま湯(40〜50℃程度)を使うと吸水が早まって便利。
たったこれだけでも炊きあがりの食感が劇的に変わるんです。
また、長時間浸水することで、玄米に含まれるフィチン酸という栄養素の吸収阻害物質が減少すると言われています。
つまり、食感が良くなるだけでなく、栄養面でも一石二鳥なんです!
栄養価を意識して玄米を取り入れている方には、この効果も見逃せません。
さらに、浸水中に1〜2回水を替えると、雑味やぬかのにおいも抑えられて、すっきりした味わいになりますよ!
ついでに、ぬか臭さが気になる人は、米を軽くもみ洗いしてから浸水させるのもおすすめ。
これだけで炊きあがりの風味がぐっと向上します。
私もこのステップを怠っていたときは、「芯が残る」「パサパサする」とガッカリしてました。
でもちゃんと浸水したら、一気にプロっぽい仕上がりに!
やっぱり基本が大事なんですね。
しかも、浸水時間をしっかり確保することで、後の炊飯工程がグッと楽になるのもポイント。
炊飯器任せでいけるし、手間も少なくて済むんです。
慣れないうちは面倒に感じるかもしれませんが、一度習慣にしてしまえば苦じゃなくなりますよ。
炊飯器だけじゃない!圧力鍋を使った時短&ふっくら術

時間がない!でもふっくら美味しい玄米炊き込みご飯を作りたい!そんなときの強い味方が「圧力鍋」です。
圧力をかけることで、玄米が短時間で芯までしっかり加熱され、もちっとした食感に仕上がります。
たとえば、通常12時間の浸水が必要なところを、圧力鍋ならたったの2〜3時間の浸水でもOK。
忙しい朝に下ごしらえして、夜にはあったかい玄米ご飯が食べられるというのは、かなりの時短になります。
時間がない人や育児・仕事で忙しい方にとっては、かなり嬉しい調理アイテムです。
さらに、圧力鍋を使えば、炊き込みご飯にありがちな“芯残り”や“水分ムラ”が起きにくいという利点もあります。
しっかりと圧力がかかることで、玄米の奥まで水分と熱がしっかり届き、結果としてムラのないふっくらご飯に仕上がります。
圧力鍋を使うコツは、水加減と蒸らし時間。
水は玄米1合に対して1.3〜1.5倍程度が目安。
具材の水分も加味して調整しましょう。
加圧後は自然放置で10〜15分ほどしっかり蒸らすことで、水分が均一に行き渡り、よりふっくらした炊き上がりに。
また、玄米だけでなく、雑穀米やロウカット玄米などとブレンドしても美味しく炊けるのが圧力鍋の強み。
味のバリエーションが広がるのも魅力の一つです。
私は休日に多めに作って冷凍しておく派なんですが、圧力鍋で炊いた玄米って、解凍してもふっくら感が残ってるのが最高なんですよね!
忙しい日の時短ランチや夜食にもぴったりで、「作り置きなのに美味しい」が叶うんです。
おすすめ具材はこれ!きのこ・鶏肉・根菜で風味アップ

「何を入れるか」で炊き込みご飯の仕上がりは大きく変わります。
特におすすめなのが「きのこ」「鶏肉」「根菜」。
この3つは、玄米の香ばしさや歯ごたえと抜群にマッチして、味も食感も大満足な炊き込みご飯に仕上がります。
きのこ(しめじ・舞茸・しいたけなど)は旨味成分であるグアニル酸が豊富。
これが加熱されることで、玄米全体にじんわりとコクを与えてくれるんです。
特に舞茸は香りが強く、少量でも味に深みを出せるので重宝します。
鶏肉は、もも肉だとジューシーに、胸肉だとさっぱりと仕上がります。皮ごと入れると脂のうまみも出るので、風味にこだわるなら皮付きがイチオシです。
さらに、にんじんやごぼう、れんこんといった根菜は、甘みと香ばしさが引き立ち、全体の味わいにやさしさと奥行きを加えてくれます。
れんこんはシャキっと感が楽しくて、アクセントになりますよ。
それぞれの具材は小さめに切るのがポイント。
大きすぎると火の通りが悪くなったり、水分の出方にムラが出たりするので、1〜2cm程度がちょうどいいサイズ感です。
具材を入れる順番も意外と大切で、鶏肉は下、野菜は上に置くことで熱が均一に入りやすくなります。
私は定番の「鶏ごぼう+しめじ」に落ち着いてますが、たまにツナ缶や干しエビを使うと一気に味変できて飽きがこないんです♪
あと、おすすめしたいのがとうもろこしや枝豆。
冷凍でもOKで、色どりもキレイだし甘みがプラスされてお子さんにも好評ですよ〜。
そのほかにも玄米の炊き込みご飯のレシピはネットでも豊富に紹介されていますので、自分の好みに合う玄米の炊き込みご飯を試してみてください。
「玄米モード」がない炊飯器でも美味しく炊ける裏ワザ

「うちの炊飯器、玄米モードがないんだよな〜」という方、安心してください。
ちょっとした工夫で、白米モードでもふっくら玄米炊き込みご飯が作れます!
実際、多くの家庭用炊飯器は白米モードでも十分な火力を持っているので、手順さえ工夫すれば、驚くほど美味しく炊き上がります。
まず、しっかり長時間浸水させること。
これで白米モードでもある程度やわらかくなります。
理想は10〜12時間以上ですが、急ぎのときはぬるま湯を使うと吸水が早まり時短になります。
そして、水の量は通常よりやや多めに(1.3〜1.5倍)設定しましょう。
具材を入れる場合は、その水分量も計算に入れて微調整をすると、べちゃつきを防げます。
最後に、少量の塩を加えるのがポイント!
塩には吸水を促進する作用があり、玄米がよりやわらかくなりやすくなるんです。
小さじ1/3程度でOK。さらに、出汁を加えることで味に奥行きも出せますし、めんつゆを少量加えると手軽に味が整います。
炊き上がり後の「蒸らし」も忘れずに。
10分ほど蓋を開けずに放置するだけで、全体の水分が均一になり、ふっくら感が増します。
さらにその後、しゃもじで優しくほぐしてからもう2〜3分蓋をしておくと、全体のなじみがよくなり、驚くほど食感がまとまりますよ。
私も最初は「炊飯器に任せっきり」だったんですが、こういった一手間で驚くほど美味しくなったので、ぜひ試してみてください!
特別な機能がなくても、ちょっとの工夫でごちそう玄米ご飯が叶います♪
玄米の炊き込みご飯がまずいのまとめ
ここまで読んでくださってありがとうございます!
「玄米の炊き込みご飯がまずい」と感じていたあなたも、きっと今日からはリベンジ成功できるはず。
次はどんな具材で炊こうかな〜なんて、楽しみながらチャレンジしてみてくださいね♪